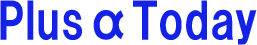-
映 画
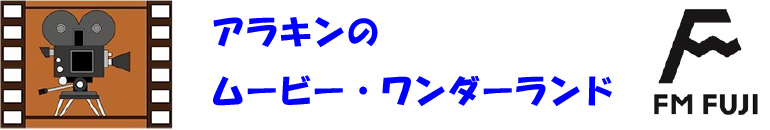
「ドンバス」「a-ha THE MOVIE」のとっておき情報
(2022年5月25日11:00)
映画評論家・荒木久文氏が「ドンバス」と「a-ha THE MOVIE」のとっておき情報を紹介した。
トークの内容はFM Fuji「Bumpy」(月曜午後3時、5月16日放送)の映画コーナー「アラキンのムービー・ワンダーランド」でパーソナリティ・鈴木ダイを相手に話したものです。

鈴木 さあ、今日はなんと荒木さんにスタジオに来ていただきました。
荒木 こんにちは!!お久しぶりです。何年かな?コロナ前に来たきりだから2年ぶりでしょうか?
鈴木 今週と来週は荒木さんがスタジオに来られて、鈴木ダイと対面トークというわけです。荒木さんと生でお話するのが面白いですよね。
荒木 そうですねー。今日はね、せっかくスタジオからなので明るく、楽しく心躍るような作品とおもいましたが、あえて、今見るべき映画と思い、ウクライナ・ロシア関連の作品からご紹介します。
タイトルは「ドンバス」。あのウクライナの東、いま世界中の注目を集めている地域、「ドンバス地方」のドンバス。ズバリです。この地名おなじみですよね。
鈴木 ニュースでよく聞きますよね。
荒木 しょっちゅうニュースに出てきますよね。激しい戦闘が行われているウクライナ東部の2014年にウクライナから独立しようとして、新ロシア派が作った「ドネツク」と「ルガンスク」の二つの国、この独立をロシアが支援という理屈になっているんですが、もともと「親ロシア派」のというと、ウクライナ人の中のロシア派と思いますが、本当はウクライナはかつてロシアの一部にされたので多くのロシア人たちが入植したんですね、それでロシア人が多い地区が形成され、「ロシアに入りたい」っていうことで独立をしたということで、もともとロシア人と言っていいんでしょうね。新ロシア派というのは…。
それで結局、彼らが地域の政権を取っちゃうんですね。そしてドネツクとルガンスクという親ロシア派政府というのを勝手に作って政治を行っているんですが、この二つの国、地域を「ドンバス」ということになります。「マリウポリ」もドンバスの重要な都市のひとつです。
今回公開される映画「ドンバス」というのは4年も前にここを舞台に作られた、現在を予言したかのような劇映画、フィクションでなんとブラックコメディで、話題になっているこの地域の政治や社会を、風刺を交えながら描いた作品。
監督はウクライナ人のセルゲイ・ロズニッツァという人です。
鈴木 ウクライナ映画ですか?
荒木 そうですね。2時間ぐらいの中に、13ぐらいの物語が入っていて、それぞれがかすかにつながってゆくというパターンです。それぞれが非常にシリアルなコントみたいになっているんですよ。
さっき言ったように、ドネツクとルガンスクのいわゆる新ロシア派政府というのを勝手に作って政治を行うんですけど、それがめちゃでたらめだ、ということが描かれています。
その中のユニークなのが、その政府が役者を動員して、フェイクニュースを作る撮影現場のシーンです。
鈴木 ありそうな話ですよね。
荒木 バスの爆破シーンを撮影して、町の人が集められた人たちがいて。テレビカメラの前で泣きながら「大変な爆発が起った、ウクライナのテロリストの仕業よ」と言わせてウクライナのテロをでっち上げているとか、っていうシーンなんですよ。
もうひとつは 車を盗まれた男が新ロシア派の警察に行くと、車は警察官が乗っているんです。返してというとはいお金と請求されます。渋っているとその金額が値段がどんどん上がっていくというそんな笑えないものも多いエピソードがつづられています、
私も見せていただきましたが、とにかく戦車や装甲車も使ったり、爆弾バンバンそれにワンカットの映像が多いのでリアリティが半端じゃありません。
このロズニッツアという人、ドキュメントが得意の監督なのでどうかすると、ドキュメントかなと思うほどです。でたらめなことがまかり通っているんですね。これは全部、実話がもとになっていると言っているんです、YouTubeやインスタとかに上がっていた映像や会話から取り、実際に体験した人の話など全部、本当のこと、それを俳優さんたちに演技させたって言っています。これはすごい内容でね。
鈴木 そうなんですか?
荒木 この監督は日本では去年あたりからドキュメンタリーが得意な監督なので『群衆』というタイトルの3部作が公開されているんですよ。「粛清裁判」とか「国葬」とか、いわゆるスターリニズム、旧ソ連時代のドキュメンタリーなんですけど、どれも長くて難解なところもあるんですが…。
鈴木 戦争とか政治に関する映画をよく撮っている方なんですか?
荒木 そうですね。ドキュメンタリーが多いですね。「マイダン革命」の記録映画なんかも撮っています。私も観ましたけど、これとっても興味深くて面白かったです。
「ドンバス」はその年のカンヌの監督賞を受賞したんですね。
今回のウクライナ侵略についての政治的発言もいくつかしています。
面白い劇映画でブラックコメディですから絵空事なんですけど、問題なのは、今大ちゃんがおっシャ多様に、それが今、事実になっちゃっているということなんです。もう予言していたかのような、シャレにならない、そういうものが映っているということなんですよね。こういうものを観ていると、
ドンバス』は今日のウクライナ・ロシア情勢を語る上で欠かせない背景です。クライシスアクターを使った情報戦も描かれ、とても4年前の映画と思えません。
鈴木 映画を作っている4年前にもうそういう火種があったということなんですね?
荒木 そうですね。ちょっと脱線しますが、ウクライナっていう国はですね、映画史的にはすごく重要な作品が各都市を舞台に作られているんですよ。代表的なのは1925年、無声映画の時代なんですが『戦艦ポチョムキン』という作品。ソ連のエイゼンシュテインという監督が作ったもの、教科書みたいな映画なんですけど。黒海に面した町・オデッサ。海の近くですね。オデーサと今は言われていますけど。「モンタージュ理論」だとか「オデッサの階段」という映画関係の学校や教科書には必ず載っているような、そういう映画が撮影されたとこなんですね。
あと 前にもお話しましたが、南部ヘルソン。ソフィア・ローレンの『ひまわり』がこのあたりのヘルソンで撮影されてるんですね。
とにかく戦争は絵空事、映画だけで済ませてほしいですね。
ということで、緊急公開 ウクライナ戦争関係の映画「ドンバス」5月21日からの公開です。
鈴木 笑っていいのか、いけないのか、微妙なところですよね。
荒木 ほんとにシリアスで、ドキュメンタリーと見まごうばかりです。
さあこのところお送りしているミュージッシャン・ドキュメンタリーシリーズ今日は5月20日公開の「a-ha THE MOVIE」です。a-haです。
1985年にリリースしたデビュー曲「Take on Me」が世界的ヒットを記録したノルウェー出身のポップグループ「a-ha」の軌跡をたどったドキュメンタリー。
詳しいことはあとでダイちゃんに詳しく説明していただけると思いますが。
a-haは、1982年、ノルウェーのオスロで、モートン・ハルケット、ポール・ワークター、マグネ・フルホルメンの3人によって結成されました。デビュー曲「Take on Me」は革新的なミュージックビデオが大きな話題を呼び米ビルボードで1位を獲得しましたね。

鈴木 アニメのあれ、強烈でしたよね。
荒木 多分 あのコンセプトを一部、映画にも取り入れていますよね。
ファーストアルバム「ハンティング・ハイ・アンド・ロウ」(Hunting High and Low)は全世界で1100万枚以上もの売上を記録し、瞬く間にスターダムを駆け上がったんですが、その後もヒット曲を次々と世に送り出します。3人の出会いとバンド結成、狂騒の80年代から90年代、解散と再結成を経て今なお進化を続ける彼らの姿を描き出すという…。ダイちゃん、彼らとの出会いは?
鈴木 1985年、僕は大学に入る前の年ですからもうポップ・ミュージックというかロックリズナーとしてはかなりなキャリアを積んでいましたね。その時 登場したノルウェー出身の3人組グループということで、ノルウェーのグループが全米のチャートを駆け上がっていくという様をまざまざと見たということは音楽としては初で…。
荒木 あまり前例がないですよね?
鈴木 ノルウェーですからね、アメリカ、イギリス、あとはオーストラリアぐらいのネットワークですからね。この「テイク・オン・ミー」(TAKE ON ME)がチャートを駆けあがっていくわけですよ。
荒木 そこ、見ていたわけ?
鈴木 そう、見ていたわけですよ。今週何位だろう 来週…そして1位になって、それにMTVで、あの時代なのでアニメの強烈な映像を見て、映像も素晴らしいポップなメロディにも夢中になって耳からも目からも楽しめましたよね。
その頂点を見たという懐かしい時代ですよ。
荒木 3人、皆個性も豊かですし、ビジュアル系バンドと捉えられていたということもあったわけですかね?
鈴木 ボーカルのモートン・ハルケートが、あまりにもイケメンすぎるんですよ。イケメンすぎるゆえにほかの二人のメンバーと微妙な差のラインが出て来て、映画でも描かれているんですけど、モートンだけ前に出て来て撮影されているが、ほかの二人はミュージッシャン気質で、ロック・ミュージッシャンでいたいんですよ。
荒木 職人ぽいですよね。下手したら後ろ向いて演奏していますものね。
鈴木 そうそう モートンだけ目立っているんですけれども、モートンの音声自体も本当に素晴らしくて、レンジが広くって…。
荒木 低音から高音に響く…ね。
鈴木 それをもっと生かしてくれという、プロデューサーやディレクター
からの指示が入る様もあって・・・モートンが、その武器を使ううれしい戸惑いがありながら、三人がノルウェーの田舎から出て来てイギリスやアメリカで大ブレイクするという、それでまた戸惑っているという様子が印象に見えましたけどね。
荒木 三人がそれぞれ目立ちたがったり、目立つのがOKという人とそうじゃない人といますから・・バンドにあり勝ちですよね。
鈴木 それで3人組というのは一番問題が起こるんですよ。ジャムも、クリームもポリスも・・・三人組というのはふたりと別の一人という組み合わせになってしますんですね。4人組は2人と2人に分かれますが、3人組は難しいですよね。
でも仲が悪いというか、緊張関係にあるほうが、アートを作るにはいいんですよ。
我々みたいな関係はアートにならないんですよ、緊張感の問題で…。
荒木 お互いにいいよ、良いよ、それで…というふうになっちゃう…。
鈴木 いいんじゃね、荒木さん とりあえず飲みにいこーってなっちゃう・・とやっているとアートにはなりにくいですよね。緊張感があったほうが作品を作る連中にはいいと思いますよ。
荒木 久しぶりにa-haを見たんですけど、さすがに老けたなーという感じですね。
鈴木 確かにね。
荒木 特に仲が良いわけでもない人たちがこの年齢になると冷静に自分たちの人間関係を分析したり、とらえたりしているんですね。
鈴木 俺は「a-ha」なんだと自分を受け入れるさまが、成長を見ている感じで…。
荒木 程よい距離感だからこそ成り立っているバンドの妙というかそういうものありますよね。 また、ジレンマがひとつの見どころみたいなこともありますよね。
…ということで今日は「a-ha THE MOVIE」。5月20日公開の作品をご紹介したんですけど…。
鈴木 「a-ha」の音楽はポップ・ミュージックの極みだとは思うのですが、今になって思うんですけどね パンフにもありますが、コールド・プレイ、U2 オアシスなんかがリスペクを公言しているんですね。
あと、ザ・ウィークエンドなんか、最近の大ヒットに「テイク・オン・ミー」のテイストをたっぷり盛り込んでいるんですけど、昔はロックファンであればあるほどa-haが好きなどというのが何となく憚れるような、「え、お前そんなの利いてるの?」みたいな雰囲気があったんですけど、ここ数年 今になってみるとa-ha 大好き ABBA大好きみたいな、この辺りはしっかりと声を大にして言えるような、音楽的土壌も豊かだったという評価が、しっかりと根付いているような感じがします。
荒木 リアルで見たことのあるリスナーの方も若い方も見ていただきたいですね。
鈴木 絶対夢中になる、素晴らしいポップ・ミュージックだと思いますよ。
荒木 MVにオマージュをささげているような感じもありますので、是非楽しんでみていただきたいと思います。今日は5月20日公開の「a-ha THE MOVIE」でした。
鈴木 荒木さん、ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。

■荒木久文(あらき・ひさふみ)1952年長野県出身。早稲田大学卒業後、ラジオ関東(現 RFラジオ日本)入社。在職中は編成・制作局を中心に営業局・コンテンツ部などで勤務。元ラジオ日本編成制作局次長。プロデューサー・ディレクターとして、アイドル、J-POP、演歌などの音楽番組を制作。2012年、同社退職後、ラジオ各局で、映画をテーマとした番組に出演。評論家・映画コメンテイターとして新聞・WEBなどの映画紹介・映画評などを担当。報知映画賞選考委員、日本映画ペンクラブ所属。
■鈴木ダイ(すずき・だい)1966年9月1日生まれ。千葉県出身。日本大学芸術学部演劇学科卒。1991年、ボストン大学留学。1993年 パイオニアLDC株式会社(現:ジェネオン・ユニバーサル)入社 し洋楽宣伝プロモーターとして勤務 。1997年 パーソナリティの登竜門であるJ-WAVE主催のオーディション合格 。
現在は、ラジオパーソナリティとして活躍するほか、ラジオ・テレビスポット、CMのナレーション、トークショー司会やMCなど、幅広く活躍。 古今東西ジャンルにこだわらないポピュラー・ミュージックへの傾倒ぶり&造詣の深さ、硬軟交ぜた独特なトーク、そしてその魅力的な声には定評がある。